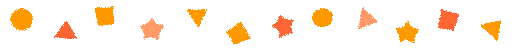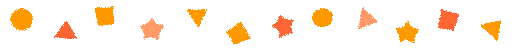Ⅲ 実践例2
2 小中学校教員交流研修
教員交流を通して、小中学校相互の教育活動・児童生徒指導等の理解を推進し、教員としての資質向上を目的にしている。異校種の学校で授業参観や授業(TT)を行い、その体験を各校に戻り現職教育等で報告発表する。
(1)交流事業実践までの流れ
・ 栃木市教育研究所研究員研修会で交流事業を各学校で行うことを決定(6月)
・ 三校の校長の話し合い(6月)
・ 教務主任による日程調整(7月)
・ 事前打ち合わせ(9月)
・ 交流事業研修(9月、10月)
(2)小中学校教員交流研修の実践報告
① 平成20年9月5日(金) 栃一小より1名栃西中に1日勤務
ア 研修の目的(研修者として)
中学校における教育活動を観察・体験することで中学校教育に関する理解を深め、教員としての視野を広げ、小中学校の連携をいっそう図れるようにする。
イ 研修内容
| |
研修内容 |
| 朝の会 |
1年5組 参観 研修者の自己紹介 |
| 1校時 |
1年1組 授業参観 国語「文節と文節の関係」 |
| 2校時 |
2年2組 授業参観 国語「用言の活用」 |
| 3校時 |
3年2組 授業参観 国語「武蔵野風景」(説明文) |
| 4校時 |
2年1組 授業参観 国語「湯桶読み、重箱読み」 |
| 給 食 |
1年5組 給食指導 |
| 5校時 |
1年5組 T.T授業 総合(トマトタイム)
「職場見学でお世話になったところへのお礼の手紙」 |
| 6校時 |
| 帰りの会 |
1年5組 参観 研修者の感想を話す |
| 放課後 |
研修の反省会 部活(吹奏楽部)の参観 |
ウ 研修の感想
学習に関して
・ 先生方の説明は丁寧で分かりやすく、生徒もよく理解していた。
・ 説明文では教材を一読するだけでも時間がかかり、これを読み解いていくのには今までの学習の蓄積が必要であると感じた。
・ 発言や発表では中学生という発達段階では個人差が出てくる。小学校で身につけていった発表やコミュニケーションのスキルを中学校で生かすよう、小中連携を進める必要がある。
小・中学校交流事業の成果と課題
・ 情報交換は今までも行ってきたが、現場で実際に中学生と接することで得られるもの、感じるものは大きかった。
・ せっかくの機会なので他教科の参観もしてみたいと思った。また、事前の打ち合わせが十分取れれば、授業もやってみたいと思った。
・ 心身共に頼もしく、たくましくなった教え子に会いその成長を間近にみることができて良かった。
② 平成20年9月9日(火) 栃西中より1名栃一小に1日勤務
ア 研修の目的(研修者として)
交流を通して、異校種間の連携をさらに密にし、発達段階に応じた国語科の学習
についての認識を深め、今後の課題を見いだす。
イ 研修内容
| |
研修内容 |
| 朝の会 |
6年2組 参観 研修者の自己紹介 |
| 1校時 |
2年1組 授業参観 国語「名まえを見てちょうだい」 |
| 2校時 |
3年1組 授業参観 国語「じゅげむ」 |
| 3校時 |
6年2組 授業参観 家庭「衣服の手入れ」 |
| 4校時 |
6年2組 T.T授業 国語 |
| 給 食 |
6年2組 給食指導 |
| 5校時 |
1年5組 T.T授業 総合(吾一タイム)
「これからの課題について」 |
| 6校時 |
| 帰りの会 |
6年2組 参観 指導 |
| 放課後 |
研修の反省会 部活(合唱部・陸上部)の参観 |
ウ 研修の感想
学習に関して
・ 小学校では低学年より学習訓練を重視し、発言、話し合い、意見を聞き考えを深める指導が発達段階に応じて行われていた。ここまで身に付いていることが中学校で生かしきれているとはいえないので、小学校で培った学習習慣とコミュニケーション能力を土台としてさらに発展していくよう指導していく必要がある。そのためにも、小中学校間での教科指導についての話し合いがあるとよい。
小・中学校交流事業の成果と課題
・ 打ち合わせの段階から学校の状況や生徒についての情報交換ができたことが非常に有益だった。特に中学1年生は入学してから最初の学期が終了し、問題が見えてきてその対応を検討している時期だったので大きな意義があった。
・ 小学校の子供たちの学習の様子やスキルの習得の様子が分かったので、それを生か
して中学校でのスキルを具体的に考えて、見通しを持った指導をしていくことが望ましい。
③ 平成20年9月29日(月) 栃西中より1名栃五小に1日勤務
ア 研修の目的(研修者として)
異校種間の交流を通して、地区内の小中学校の連携をさらに密にし、児童の発達段階に対する認識を深め、今後の課題を見いだす。
イ 研修内容
| |
研修内容 |
| 朝の会 |
3年4組 参観 研修者の自己紹介 |
| 1校時 |
3年4組 授業参観 国語 漢字テスト、「木の葉」音読 |
| 2校時 |
3年4組 授業参観 図工 お話の絵「虹のはしがかかるとき」 |
| 3校時 |
3年4組 T.T授業 算数「水のかさ」 |
| 4校時 |
3年4組 授業参観 体育「いろいろな動き」 |
| 給 食 |
3年4組 給食指導 |
| 5校時 |
3年4組 授業参観 社会 農家の仕事「いちごができるまで」 |
| 帰りの会 |
6年2組 参観 指導 |
| 放課後 |
校舎見学 部活(陸上部・相撲部)の参観 |
ウ 研修の感想
小学校の様子全般を通して
・ 小学校では学級担任制で、一日を通して一つのクラスを指導している。クラスの児童の様々な面が見られる点でとても有効である。しかし、一人の教員だけでの関わりでは難しい場面も想定されるし、中学校での教科担任制にギャップを感じさせないためにも、高学年につれて出授業が多くなることは大切だと思った。
小・中学校交流事業の成果と課題
・ 今回3年生の参観であったが、学年が上がるにつれて発達の様子ををさらに知ることができれば、小学校から中学校へのつながりについて、教員自身がさらに意識できると思う。今言われている、中1ギャップ解消のためにも中学校教員が小学校での児童の様子を理解することが大切であると思う。
・ 逆に小学校の先生方も中学校で求められるものを知っていただき、意識することが大切であると思う。交流の後、それぞれの感じた感想や課題をもちより、直接話し合う機会があるとさらに連携が図れると思う。
④ 平成20年10月1日(水) 栃五小より1名栃西中に1日勤務
ア 研修の目的(研修者として)
小中学校の交流を通して、主に理科の授業を参観し、理科の授業の指導法について研修する。また。卒業生ともふれ合うことで、交流を深める。
イ 研修内容
| |
研修内容 |
| 朝の会 |
1年4組 参観 研修者の自己紹介 |
| 1校時 |
1年4組 授業参観 理科「音の発生と伝わり方について」 |
| 2校時 |
2年3組 授業参観 社会「アメリカ合衆国の農業地域と工業地域」 |
| 3校時 |
1年3組 授業参観 理科「音の大小と高低について」 |
| 4校時 |
1年1組 授業参観 理科「音の発生と伝わり方について」 |
| 給 食 |
1年4組 給食指導 |
| 5校時 |
1年2組 授業参観 理科「音の大小と高低について」
表彰集会 |
| 6校時 |
| 帰りの会 |
1年4組 参観 指導 |
| 放課後 |
事務処理 |
ウ 研修の感想
・ねらいをはっきり提示した授業で、何について学習すべきかが分かりやすかった。教材教具の工夫がすばらしかった。
・板書が思考の流れに沿って大変分かりやすく工夫されていた。先生方が専門的で、幅広い知識をもっておりすばらしかった。
・中一の生徒と接することが多かったが、6ヶ月間の成長を感じた。
・教師としての日々の努力の大切さを学んだ。
※ 実施方法についての詳細は、小中学校教員交流研修マニュアルをご覧ください。
栃木市教育研究所小中連携部会